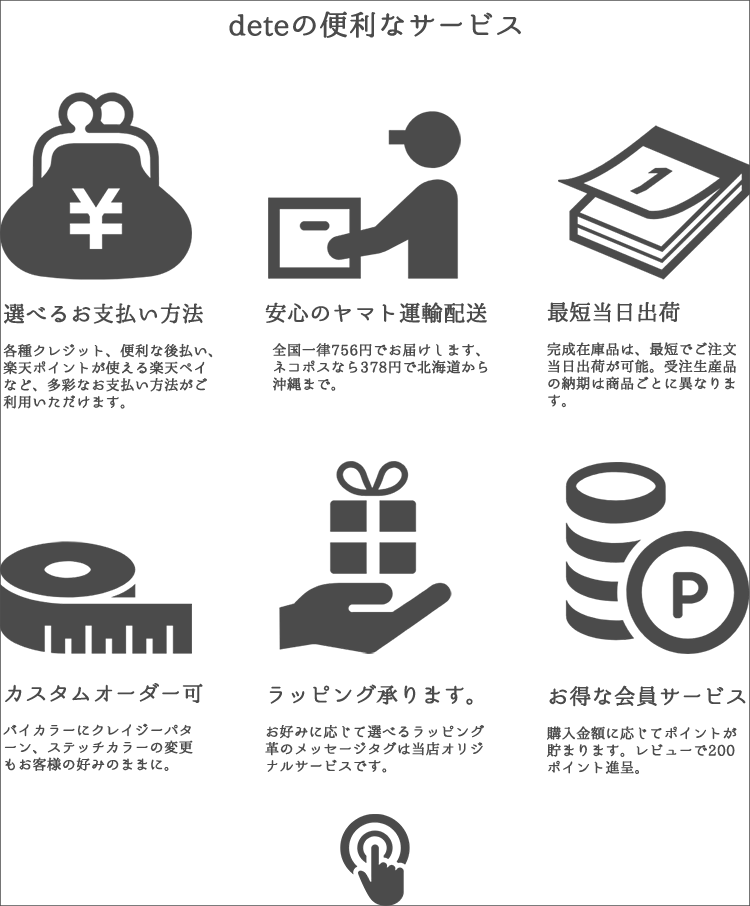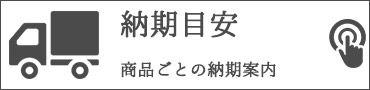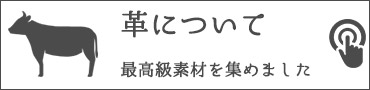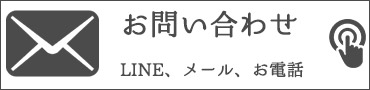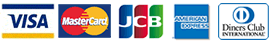アトリエと使用工具
アトリエ紹介

築80年を越える工房で制作しています。







在庫品の販売やオーダーメイドのご注文を受け付けております。
一人で運営しておりますので、急にお越しいただくと対応することができない場合がございます。お手数ではございますが、訪問いただく前に必ずご一報をお願いいたします。
浦和駅から徒歩10分
湘南新宿ライン・京浜東北線・宇都宮線・高崎線・上野東京ライン (池袋駅→浦和駅19分 、新宿駅→浦和駅25分、東京駅→浦和駅24分)
※駐車場はございません。公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
・不定休 ・営業時間 12:00~19:00
・要予約(一人で運営しております都合上、事前にご来店日時のご予約をお願いしております)
道具紹介1 包丁


- 2014.09.24
- 15:34
道具紹介2 菱錐



- 2015.11.19
- 23:07
- コメント (2)
道具紹介3 菱目打ち
工具紹介の第3回目。
菱錐と同じく、基本的にミシン縫いには不要ですが手縫いには必要不可欠な道具。
あらかじめ引いておいた縫い線に沿ってこの菱目打ちをあて、木槌などで叩いて革に縫い穴をあけます。
穴をあけるといっても、この道具で穴を深く空けてしまうと表面の縫い穴が広がってしまい、縫い目の美しさも強度も失われてしまい本末転倒です。そこで必要になるのが、前回紹介した菱錐です。これらの道具は二つで一つ。どちらも自分に馴染むよう削り、砥ぎ上げてから使います。

以前メーカーの方に、「菱目は砥ぐ必要は無い。」と言われたことがありますが、買ったばかりの菱目と、切れるくらいに砥ぎ上げたそれとでは、縫いの正確性に明らかな差が出ます。
買ったばかりの状態でも穴をあけることはできますが、出来るだけ小さく、均等な穴を開ける為には、やはり買い手が一手間加える必要があるように思います。

直線は大きい方で。曲線部分は歯が二本の小さい方で。
次回第四回目は「念を入れる」について。
- 2014.09.23
- 16:37
- コメント (0)
道具紹介4 捻
第四回は念入れに使う道具の紹介です。
左より、
二重(ツル 薄物用 カバーが付いていて見えませんが)
二重(ツル 厚物用)
玉(ツル 薄物用)
玉(ツル 厚物用 電気)
玉アタマ(平 電気 未加工)
玉アタマ(平 電気 この一点のみ用途が違います)

捻を入れる道具といっても、縫い線を引くのに使うもの、仕上げに蜜蝋を入れ込むための物、飾り線を入れるもの、
それらを兼ねるものなど、当工房では用途によってそれぞれを使い分けています。


コバとステッチの間に入った線が捻で引いたものです。

熱でコバを引き締めつつ、蜜蝋を溶かし込んで丈夫にします。

工具のケースを作るのも楽しいです。
「念には念を入れる」という言葉の由来だという話もありますが、正確なところは定かではありません・・・。
- 2015.09.03
- 00:02
- コメント (0)
道具紹介5 ランプ&蝋
道具紹介第5回目は、前回の「念」に関連して、製品のコバや糸に溶かし込む為の蝋と、それを熱する為のランプをご紹介いたします。 |

| 蝋は、国産、豪産のいくつかや、それに松脂を加えたり、最適なものを探っています。精製された工芸用のものを試したこともあります。何分、自然のものですので、品質が安定しないのが玉に瑕です。 |

| このランプで熱した念でコバに蜜蝋を入れたり、蜜蝋を擦りこんだ麻糸を直接熱して蝋を浸透させたりと、何かと使うアナログなオイルランプです。 |

- 2014.09.23
- 16:37
- コメント (0)
道具紹介6 接着に使ういろいろ
道具紹介6回目。
今回は接着に使う3つの道具を一度にご紹介します。
接着する対象物の形や素材によって、それぞれを使い分けたり併用したりします。
~ローラー~
広い範囲をベタ貼りする際、ムラ無く圧着するのに便利です。
接着する面積によって幅の広いものと狭いものを使い分けます。

~ハンマー~ (下画像 左)
言わずと知れた金槌です。
片面は釘を打つ平面に、反対面は、叩いた痕を残さないようになだらかに出っ張った曲面でできています。古い言葉で玄翁といわれるタイプの金槌です。
局部的に強い力を加えることができるので、小さなパーツや縫い目をしっかりと接着させたい時に使います。

~エンマ~ (上画像 右)
はさむ部分が平面になっており、対象物を押しつぶす為に使われるヤットコです。
広い範囲を圧着するのには使えませんが、幅の狭い部分に使用するにはとても便利な道具です。先端には薄く漉いた革を貼り、対象物を傷つけないように配慮して使います。
この道具がなぜエンマと呼ばれているのかは、ここでうんちくの一つも語れれば、少しはさまにもなろうかと思いますが・・・。というのは、もともとエンマと呼ばれた道具は、和釘を抜く為に使われたもので、はさむ先端は平面ではなく、釘を抜くのに特化した(人差し指と親指で作るOKサインのような)形をしています。
時代と共にその釘抜きのエンマは需要が減り(現在は製靴道具店で見かけます)、どのような経緯で、革製品作りに使われるこの道具がエンマと呼ばれるに至ったのか。探ればこぼれ話の一つや二つは付いてきそうな気がして、詳しい方のお話を聞けたら楽しいんじゃないかと思います。
ちなみに、エンマ釘抜きの先端が刃になったものは食い切りといい、カシメや釘を切ったり、ファスナーのムシを切り離したりするのに使います。
 食い切り(釘抜きのエンマは食い切りの刃を潰したような形状)
食い切り(釘抜きのエンマは食い切りの刃を潰したような形状)
釘抜きのエンマと閻魔大王にゆかりがあることは言わずもがなですが、古典落語の「粗忽の使者」で、大工が侍のお尻をつねるのに使ったのもエンマです。さぞかし痛かったことと察します。
- 2014.09.23
- 16:37
- コメント (0)
道具紹介7 鉋
少し間があいてしまいましたが、工具紹介第7回目は鉋(かんな)です。
古くから使われている大工道具ですが、今はもっぱら趣味の世界で使われているに過ぎない過去の遺物なのかもしれません。
万葉集に歌われるほど古くからある道具です。
真鉇持ち弓削の河原の埋木の顕るましじき事にあらなくに
(巻七 一三八五 岩波文庫による)
「道具古事記」 前久雄著より抜粋
現在使われている(鉋の良し悪しを話題にすることもあまりないかもしれませんが・・・)字は“鉋”ですが、古くは、“鉇”、“金+施”、金+色、金+「疑」の右側部分などなど、ググっても見つけられない字があてられていました。
これらの古い字が使われていた頃、カンナは今のような“台”に刃が納められた形ではなく、数十センチはあろう長い柄に刃がついた槍鉋(ヤリガンナ)と呼ばれるもののことを指していました。その後今のカンナの原型となる台カンナが生まれ、現在に残る多種多様な鉋へと変貌を遂げました。
革もの作りでは、コバの面取り以外でも、床面(裏のボソボソ面)を整えたり、漉いたり、包丁では難しい繊細な作業に使うことが多いです。

写真のものは革用に作られた鉋です。木工道具の分類の中では、豆反鉋と呼ばれる部類でしょうか。
砥ぎがうまくいっているかどうかで、仕上がりはもちろん、作業効率も大きく違います。よく砥げた刃での作業は気持ちがいいものです。

- 2014.11.19
- 00:31
- コメント (0)
道具紹介8 菱錐2015



- 2015.11.15
- 03:37
- コメント (0)